建設機械・重機免許を徹底解説|種類・取得費用・日数

本記事では、建設業界で活躍する重機の種類や役割に加え、それぞれの操作に必要な免許の種類や取得方法について詳しく解説します。これから重機オペレーターを目指す方や、免許取得を検討している方にとって役立つ情報をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
目次
重機・建機とは?

重機とは、重工業で使用される機械や車両で、「建設機械」とも呼ばれています。
建設現場はもちろんのこと、倉庫業や製造業でも活躍する幅広いニーズのある機械です。
重機を操縦する仕事は、専門性の高い仕事の一つです。
そのため、操縦方法は機械それぞれで違うため、知識と操縦技術が必要になります。
また、現場作業は単調な作業も多いので、重機免許を持っていないと、仕事の幅はなかなか広がりません。
免許を取得し、実際に機械を動かすことで機械のそばで働く際、危険な場所などの予測ができるようになります。
重機の種類
重機の種類は数え切れないほどあります。重機の一例は、下記のとおりです。
| 名称 | おもな作業内容 |
| 油圧ショベル | ユンボなどとも呼ばれており、バケットで泥を掻き出し、整地や掘削する |
| ブルドーザー | 車両の前面にブレードと呼ばれる排土板(分厚い鉄板)があり、排土板を押す形で整地する |
| 杭打ち機 | 背の高い車両に杭をぶら下げ、上から押し込み杭を地中に埋める |
| ダンプ | トラックと同じ形状だが、荷台が持ち上がり載せていた土砂を一気に落としたり、運搬する |
| ホイールローダー | 前面に大型のバケットとバケットを持ち上げるリフトアームを備え、多くのものをすくって持ち上げる |
| 高所作業車 | クレーンの先端にカゴを取り付け、高い作業をおこなう場合に使用する |
| クレーン | 車両からブームと呼ばれる長い腕を伸ばし、先端にフックを取り付け重い荷物を吊り、持ち上げ移動する |
| ユニック車 | クレーンが搭載されている重量物を簡単に上げたり下ろしたりすることができる |
| フォークリフト | まっすぐに伸びた2本の爪がついており、パレットに挿し込み貨物を移動させる |
| ショベルローダー | まっすぐに伸びた2本の爪がついており、パレットに挿し込み貨物を移動させる |
| アスファルトフィニッシャー | アスファルトの合材を流し、道路舗装の作業に使用 |
| パッカー車 | ゴミを収集しながら圧縮していく |
このように、ひと口に重機といっても種類は多種多様です。
人気の高い重機から、見たことがないようなマイナーなものまであるため、一度も聞いたことがない名前の重機もあると思います。
重機の免許取得を目指しているなら、まずはどのような重機があり自分にはどの免許が必要なのかを洗い出すとよいです。
重機免許を取得できる最低年齢は18歳以上
重機免許の取得に関して、年齢制限のない免許は多くあります。しかし、労働基準法で定める危険有害業務をおこなえる年齢は満18歳以上のため、重機免許取得も実質18歳以上の方が対象です。
今現在、仕事として建設現場などで働いているのであれば、免許の取得条件が整っている人が多いです。
重機の操縦に必要な免許、資格、取得日数、費用

重機の操作に必要な免許や取得日数、費用は免許によって違います。今回は、人気のある資格を11個をピックアップし、詳しくご紹介します。
それぞれの資格に必要な日数や費用は、以下のとおりです。
| 資格の種類 | 日数 | 費用 |
| クレーン | 2~6日 | 4万~15万円 |
| フォークリフト | 2~5日 | 1万5,000~5万5,000円 |
| 不整地運搬車 | 1万6,000~11万円 | |
| 車両系建設機械 (整地・運搬・積み込み用及び掘削用) |
1~5日 | 2万~11万円 |
| 車両系建設機械 (解体用) |
1万~11万円 | |
| 車両系建設機械 (基礎工事用) |
2~7日 | 2万~13万円 |
| 高所作業車運転 | 2~3日 | 2万~6万円 |
| 玉掛け | 2万~4万円 | |
| ショベルローダー | 2~5日 | 3万~11万円 |
| 大型特殊自動車 | 1~7日 | 7,000~13万円 |
| ロードローラー | 2日 | 2万円程度 |
| 建設用リフト | 2日 | 1万円程度 |
それぞれの資格について、解説していきます。
【重機免許1】クレーン

クレーンは建設現場はもちろん、運送業や倉庫業でも活躍する応用幅の広い資格です。
<あわせて読みたい>
クレーン車の種類や特徴|必要な資格・免許・代表メーカーを紹介
トラッククレーン(ユニック車)とラフタークレーンの違いは?サイズ・特徴・必要な免許などを紹介
クレーンの資格(運転士免許・技能講習・特別教育)を徹底解説!取得の難易度や費用についても
| 名称 | 講習時間 | 日数 | 料金 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 16~20時間 | 3日 | 4万~5万円 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | 16~20時間 | 3日 | 4万~5万5,000円 |
| 移動式クレーン運転実技教習 | 9時間(実技時間) ※教習所によって座学もあり(16時間) |
6日 | 12万~15万円 |
| クレーン運転特別教育 | 8~13時間 | 2日 | 2万~3万円 |
小型移動式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習の試験に合格すると、つり上げ荷重5トン未満の小型移動式クレーンを操作できます。
移動式クレーンとはトラックの荷台などのように、クレーン自体が固定されていないタイプを指します。5トン未満が条件となるので小型という名称が頭についていると覚えておきましょう。
小型移動式クレーン運転技能講習の講習内容は学科13時間、実技7時間です。玉掛け技能講習終了者やクレーン・デリック運転士免許を持っていれば、一部の教習が免除されるなどの条件もあります。
さまざまな条件の方が免除対象なので、技能講習を受ける前に自分は免除対象に含まれるのかを確認しておきましょう。
<あわせて読みたい>
【資格を取りたい方必須】小型移動式クレーンの種類から講習時間や費用まとめ
床上操作式クレーン運転技能講習
床上クレーンとは、操作者が床の上で操作するタイプのクレーンのことを指し、天井に固定されているクレーンが対象です。
床上操作式クレーン運転技能講習に合格すると、つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンを操作できます。
床上操作式クレーン運転技能講習の講習内容は学科13時間、実技7時間です。
こちらも免除対象があり、下記の人が対象です。
・揚貨装置のいずれかの運転士免許
・小型移動式クレーン・デリック、玉掛けなどの技能もしくは特別教育が終了して6ヵ月以上実務経験のある方
ただし、玉掛け作業をおこなう場合、クレーンの資格とは別に玉掛けの資格が必要なので注意が必要です。
移動式クレーン運転実技教習
移動式クレーン運転実技教習の試験に合格すると、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの操作をおこなえます。ただし、公道を走行する場合、運転免許が別途必要なので注意しましょう。
移動式クレーン運転実技教習の講習内容は学科16時間、実技9時間です。学科もしくは実技どちらかがすでに修了していれば、修了した講習を免除可能となります。
クレーン運転特別教育
クレーン運転特別教育を修了すると、移動式を除くつり上げ荷重5トン未満のクレーンを操作できます。講習内容は学科9時間、実技4時間です。
玉掛け技能講習を修了した者は大幅に講習を免除できるので、合わせて取得することをおすすめします。
【重機免許2】フォークリフト

フォークリフトの免許は、倉庫業だけでなく、ホームセンターやスーパーなど日常的に利用する店でも活躍している免許です。
| 名称 | 講習時間 | 日数 | 料金 |
| フォークリフト運転技能講習 | 11~35時間 | 2日~5日 | 2万~5万5,000円 |
| フォークリフト運転特別教育 | 12時間 | 2日 | 1万5,000円~2万円 |
<あわせて読みたい>
フォークリフトの種類とは?それぞれの特徴や構造を解説|運転に必要な免許・資格・取得方法・費用について
フォークリフト免許の取得手順・費用・日数とは?あれば便利な資格取得までの流れを徹底解説!
リーチフォークリフトとは?フォークリフトの種類から操作方法やポイント|運転のコツと免許の種類
フォークリフト運転技能講習
フォークリフト運転技能講習の試験に合格すると、最大荷重が1トン以上のフォークリフト操作ができます。建設現場や大型倉庫で活躍しているフォークリフトは1トン以上のものが多く、1トン未満では使いものにならないこともあります。
そのため、フォークリフトが活躍しそうな現場で働く際は、フォークリフト運転技能講習を受講しておきましょう。
フォークリフト運転技能講習の講習内容は学科11時間、実技24時間です。大型特殊免許を持っていれば、大幅に講習を免除してもらえますが、4輪の運転免許でも免除対象となります。
技能講習を受けておけば、すべての大きさのフォークリフトが運転可能です。
フォークリフト運転特別教育
フォークリフト運転特別教育を修了すると、1トン未満のフォークリフトを操作できます。
講習内容は学科6時間、実技6時間です。
小さいフォークリフトは、スーパーなどで活躍することもあるので、必要であれば受講すると役に立ちます。
【重機免許3】不整地運搬車

不整地運搬車とは、過酷な路面状態でも走行できるよう設計された車両です。
不整地運搬車は土木現場だけでなく、足場の悪い場所にある店などへ荷物を搬送する際にも活躍する免許です。
| 名称 | 講習時間 | 日数 | 料金 |
| 不整地運搬車運転技能講習 | 11~35時間 | 2日~5日 | 4万~11万円 |
| 不整地運搬車運転特別教育 | 12時間 | 2日 | 1万6,000円程度 |
不整地運搬車運転技能講習
不整地運搬車運転技能講習の試験に合格すると、最大積載量1トン以上の不整地運搬車を操作できます。不整地運搬車運転技能講習の講習内容は学科11時間、実技24時間です。
4輪の運転免許を持ち一定の条件をクリアすれば、講習時間を24時間免除できる、免除幅の大きい資格となります。
不整地運搬車運転特別教育
不整地運搬車運転特別教育を修了すると、最大積載量が1トン未満の不整地運搬車を操作できます。
講習内容は学科6時間、実技6時間です。不整地運搬車運転特別教育は実施している機関が少ないので、取得したい方はどこで取得できるか事前に確認しておくとよいです。
【重機免許4】車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)

整地・運搬、採掘用車両系建設機械は、整地や運搬などに使用されている重機を操作できる免許です。
| 名称 | 講習時間 | 日数 | 料金 |
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用) 運転技能講習 |
6~38時間 | 1~5日 | 3万~11万円 |
| 小型車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用掘削用) 運転特別教育 |
13時間 | 2日 | 2万円程度 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の試験に合格すると、機体質量(機械本体のみの質量)3トン以上の車両系建設機械を操作できます。
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習での機械とは、下記の4つの作業に用いられる重機を指します。
・運搬
・積み込み
・掘削
ブルドーザーやパワーショベル、ホイールローダーなど、一部の重機が対象です。
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の講習内容は学科13時間、実技25時間です。車両系建設機械には、解体用など別途資格が存在します。
他の資格をすでに持っていれば大幅に時間短縮がはかれるので、段階を踏みながらそれぞれの資格を取得しておくことをおすすめします。
小型車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用掘削用)運転特別教育
小型車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用掘削用)運転特別教育を修了すると、機体質量が3トン未満の車両系建設機械を操作できます。講習内容は学科7時間、実技6時間です。
作業現場では3トン以上の重機も多く活躍しているので、免許の取得前に3トン未満なのかを確認しておきましょう。
【重機免許5】車両系建設機械(解体用)

解体用車両系建設機械は、解体に用いられる重機の操作をおこなう免許です。
| 名称 | 講習時間 | 日数 | 料金 |
| 車両系建設機械(解体用) 運転技能講習 |
3~38時間 | 1~5日 | 2万~11万円 |
| 小型車両系建設機械(解体用)運転特別教育 | 5~14時間 | 1日or2日 | 1万円程度 |
車両系建設機械(解体用)運転技能講習
車両系建設機械(解体用)運転技能講習の試験に合格すると、機体質量3トン以上の建物などを解体する際に使用する重機を操作できます。
解体用の重機は、ブレーカーや鉄骨切断機、コンクリート圧砕機などの特殊な重機です。くわえて、油圧ショベルの先端を解体用に変更すると、解体用の重機にできます。
車両系建設機械(解体用)運転技能講習の講習内容は、学科13時間、実技25時間です。また、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の資格を持っていれば、5時間の講習で取得できます。
そして、多くの教習所では5時間枠しか取り扱ってない傾向にあるので、先に車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の資格を取得し、解体用へのステップアップをおすすめします。
小型車両系建設機械(解体用)運転特別教育
車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了すると、機体質量が3トン未満の解体用重機を操作できます。講習内容は学科7時間、実技7時間です。
小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育を修了すれば、5時間の教習で取得できます。
また、14時間まるまる講習をしている団体はほとんどありません。整地等の特別教育を修了したあとに取得するのがおすすめです。
【重機免許6】車両系建設機械(基礎工事用)

基礎工事用車両建設機械は、建築物の基礎工事で活躍する免許です。
基礎工事での重機は、くい打機やくい抜機をはじめ、アースドリルやバイブロハンマーなども該当します。
聞いたこともない特殊な車両を使う機会が多いのも、基礎工事の特徴です。基礎工事用の資格は、整地・運搬・積み込みなどに比べ使用頻度は少なく、取得する人も限られてきます。
自分に必要な資格なのであれば取得をおすすめしますが、そうでないなら他の資格取得に費用や時間を回したほうが効率的です。
| 名称 | 講習時間 | 日数 | 料金 |
| 車両系建設機械(基礎工事用) 運転技能講習 |
9~39時間 | 2~7日 | 5万~13万円 |
| 小型車両系建設機械(解体用) 運転特別教育 |
13時間 | 2日 | 2万円程度 |
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習の試験に合格すると、機体重量3トン以上の基礎工事に使用される重機を操作できます。
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習の講習内容は学科14時間、実技25時間です。
また、移動式クレーン運転士免許を持っていれば9時間の講習で、大型特殊自動車運転免許保有者や不整地運搬車運転技能講習修了者、車両系建設機械(整地等)または(解体用)運転技能講習修了者は25時間で取得できます。
小型車両系建設機械(基礎工事用)運転特別教育
小型車両系建設機械(基礎工事用)運転特別教育を修了すると、機体重量が3トン未満の基礎工事用建設機械を操作できます。講習内容は学科7時間、実技6時間です。
技能講習同様、こちらの資格も取得できる場所が限られているので注意しましょう。
【重機免許7】高所作業車運転

高所作業車運転は電柱工事だけでなく、建物の窓清掃やシャッター塗装などでも活躍する免許です。高所作業車はトラックの荷台に取り付けられているタイプから、単体で操作するものまで形状はさまざまあります。
また、高所作業車は電気工事をはじめ、シャッターの清掃や塗装などの仕事で使われる、
使用頻度の高い資格です。
しかし、路面工事などではあまり使わないので、必要かどうかをよく考えて取得するのがおすすめです。
| 名称 | 講習時間 | 日数 | 料金 |
| 高所作業車運転技能講習 | 12~17時間 | 2~3日 | 3万~6万円 |
| 高所作業車運転特別教育 | 9時間 | 2日 | 2万円程度 |
<あわせて読みたい>
高所作業車の特徴や中古トラック市場での人気メーカーや中古車両購入時のチェックポイントを大紹介!
高所作業車の資格や免許とは?取得方法・更新・再発行・運転技能講習・特別教育
高所作業車運転技能講習
高所作業車運転技能講習の試験に合格すると、作業床の高さ10m以上の高所作業車を操作できます。高所作業車運転技能講習の講習内容は、学科11時間、実技6時間です。
4輪の運転免許取得者や不整地運搬車運転技能講習修了者、フォークリフト運転技能講習修了者を持っていれば一部の講習を免除できます。
高所作業車運転特別教育
高所作業車運転特別教育を修了すると、作業床の高さ10m未満の高所作業車を操作できます。講習内容は、学科6時間、実技3時間です。
しかし、10m以下の場所しか作業しない場合でも、作業床が10m以上の高さに持ち上がる重機は操作できません。
そのため、操作する前に何mまで持ち上がるのかを確認しておきましょう。
【重機免許8】玉掛け

玉掛けは、クレーン作業において、荷物をつり上げる際必須の免許です。玉掛け業務はクレーンの操縦士との呼吸が大切です。
万が一、つり上げたクレーンから貨物が落ちてしまうと、死亡事故につながる可能性もあるからです。そのため玉掛け資格を取得するのであれば、しっかりとクレーンの勉強もする必要があります。
| 名称 | 講習時間 | 日数 | 料金 |
| 玉掛け技能講習 | 15~19時間 | 2~3日 | 2万~4万円 |
| 玉掛け特別教育 | 9時間 | 2日 | 2万円程度 |
<あわせて読みたい>
玉掛け合図を画像付きで詳しく解説!玉掛けの合図に必要な資格や注意点も合わせて紹介
玉掛け技能講習
玉掛け技能講習の試験に合格すると、つり上げ荷重が1トン以上あるクレーンの玉掛けをおこなえます。玉掛け技能講習の講習内容は、学科12時間、実技7時間です。
小型移動式クレーン運転技能講習や床上操作式クレーン運転技能講習など、クレーンの資格を持っていれば有利なので、クレーンの資格と一緒に取得することをおすすめします。
玉掛け特別教育
玉掛け特別教育を修了すると、つり上げ荷重が1トン未満のクレーンへ玉掛けをおこなえます。講習内容は学科5時間、実技4時間です。
1トン未満のクレーンであれば、どのような形状のクレーンへの玉掛けもおこなえます。
【重機免許9】ショベルローダー

ショベルローダーは、整地作業においてショベルローダーを使用する際、活躍する免許です。建設機械の整地・運搬用の資格では操作できません。
ショベルローダーに似た重機でホイールローダーがあります。よく似ており、使用方法も同じことから、ショベルローダーの免許を持っていればホイールローダーも運転できると勘違いしてしまう人もいます。
しかし、ショベルローダーの免許では、ホイールローダーは運転できません。その逆も同様で、ホイールローダーを運転したいのであれば、整地・運搬・積み込み用及び採掘用建設機械の講習を受ける必要があります。
簡単な見分け方は、車両が曲がる際、前後どちらのタイヤが横を向いているかを確認する方法です。ホイールローダーは一般的な車と同じ前輪駆動なので、前のタイヤが向きを変えます。それに対し、ショベルローダーはフォークリフトのように後輪駆動なので、曲がる際は、後輪の向きが変わります。
このように見分ければ、勘違いを防げます。
| 名称 | 講習時間 | 日数 | 料金 |
| ショベルローダー等運転技能講習 | 9~35時間 | 2~5日 | 3万~11万円 |
ショベルローダー等運転技能講習
ショベルローダー等運転技能講習の試験に合格すると、最大荷重1トン以上のショベルローダーを操作できます。ショベルローダー等運転技能講習の講習内容は学科11時間、実技24時間です。
4輪の運転免許取得者や大型特殊自動車運転免許保有者は、講習を一部免除できます。
【重機免許10】大型特殊自動車

| 名称 | 講習時間 | 日数 | 料金 |
| 大型特殊自動車技能教習 | 7時間(検定含む) ※取得方法によっては講習が不要な場合も |
1~7日 | 7000円~13万円 |
<あわせて読みたい>
大型特殊免許で運転できる車両(大型特殊自動車)|費用・日数・限定解除方法
大型特殊免許を取得するために必要な日数や費用、コツなどを徹底解説!どんな車が該当するの?
大型特殊自動車技能教習
大型特殊自動車技能教習の試験に合格すると、小型特殊自動車以外の特殊自動車を公道で走行できます。同時に運転免許も必要となる資格なので注意が必要です。
また、大型特殊免許を持っていても特殊自動車の操作はできません。あくまで公道で運転する場合に必要な免許であり、操作には別の資格が必要です。大型特殊自動車技能教習の教習内容は実技6時間、検定1時間です。
取得方法は、教習所での取得が一般的ですが、免許センターへ行き一発試験を受ける方法もあります。教習所で取得するなら決められた講習を受けなければなりませんが、一発試験であれば講習は必要ありません。
どちらにもメリットとデメリットがあるので、リスクも考えて取得方法を選びましょう。
【重機免許11】ロードローラー

ロードローラーは、地盤を固める作業においてロードローラーを使用する際に必要な免許です。
| 名称 | 講習時間 | 日数 | 料金 |
| ローラー(締固め用)特別教育 | 10時間 | 2日 | 2万円程度 |
ローラー(締固め用)特別教育
ローラー(締固め用)特別教育を修了すると、締固め(しめかため)用の重機を操作できます。講習内容は学科6時間、実技4時間です。
締固め用の重機とは、タイヤーローラーやハンドガイドローラーなどローラーを持つ特殊な車両のことを指します。大きなローラーにより土地を平らにし、道路を舗装したり建物の基盤を作ったりします。
【重機免許12】建設用リフト

建設用リフトとは、建設現場で資材や作業員を高所へ運搬するための昇降装置のことを指します。工事現場の高層化や効率的な作業のために使用され、特に建築工事や改修工事の現場でよく見られます。
| 名称 | 講習時間 | 日数 | 料金 |
| 建設用リフト特別教育 | 9時間 | 2日 | 1万円程度 |
建設用リフト特別教育
建設用リフト特別教育を修了すると、建設現場で使用されるリフト(資材運搬用や人荷共用リフトなど)の運転・操作がおこなえます。操作ができるのは、積載荷重0.25t以上でガイドレールの高さが10m以上の建設用リフトです。建設用リフト特別教育の講習内容は学科5時間、実技4時間です。
建設用リフト特別教育を取得することで建設現場での業務の幅が広がり、キャリアアップにもつながります。
重機免許に関しての注意点

重機では同じような名称の免許が多くあります。しかし、免許によって作業できる重機の種類が違ったり、操作できる重機の大きさに制限があったりと、条件はまちまちです。
そのため免許の取得前には、自分が必要な免許や資格は何があるのかを洗い出す必要があります。
また、本記事でご紹介している資格のほとんどは、私有地や現場で運転や操作できる資格です。そのため、公道を走行できるわけではありません。
もし、公道で走行が必要な場合、それぞれの車両に見合った運転免許を取得する必要があります。
長期労働者は安全衛生教育を定期的に受けなければならない
重機操作の仕事に長期間携わっている人は、定期的に安全衛生教育を受けなければなりません。安全衛生教育とは、資格取得から期間があいてしまい、基本的な危険回避方法などを忘れないようにおこなう教育です。安全衛生教育は、労働安全衛生法により受けることが義務付けられています。
教育内容や受講期間は、資格によって違います。
例えば、フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育は、技能講習の資格を取得して5年を経過した方が対象であり、玉掛け業務従事者安全衛生教育は玉掛けの技能資格を取得して5年経過している方が対象です。
安全教育のなかには、10年経過後におこなうものもあり、資格による期間の違いも特徴です。事業者が従業員に定期的に受けさせる教育なので、従業員が個人で受ける必要はありません。
あわせて持っておけば有利になる資格
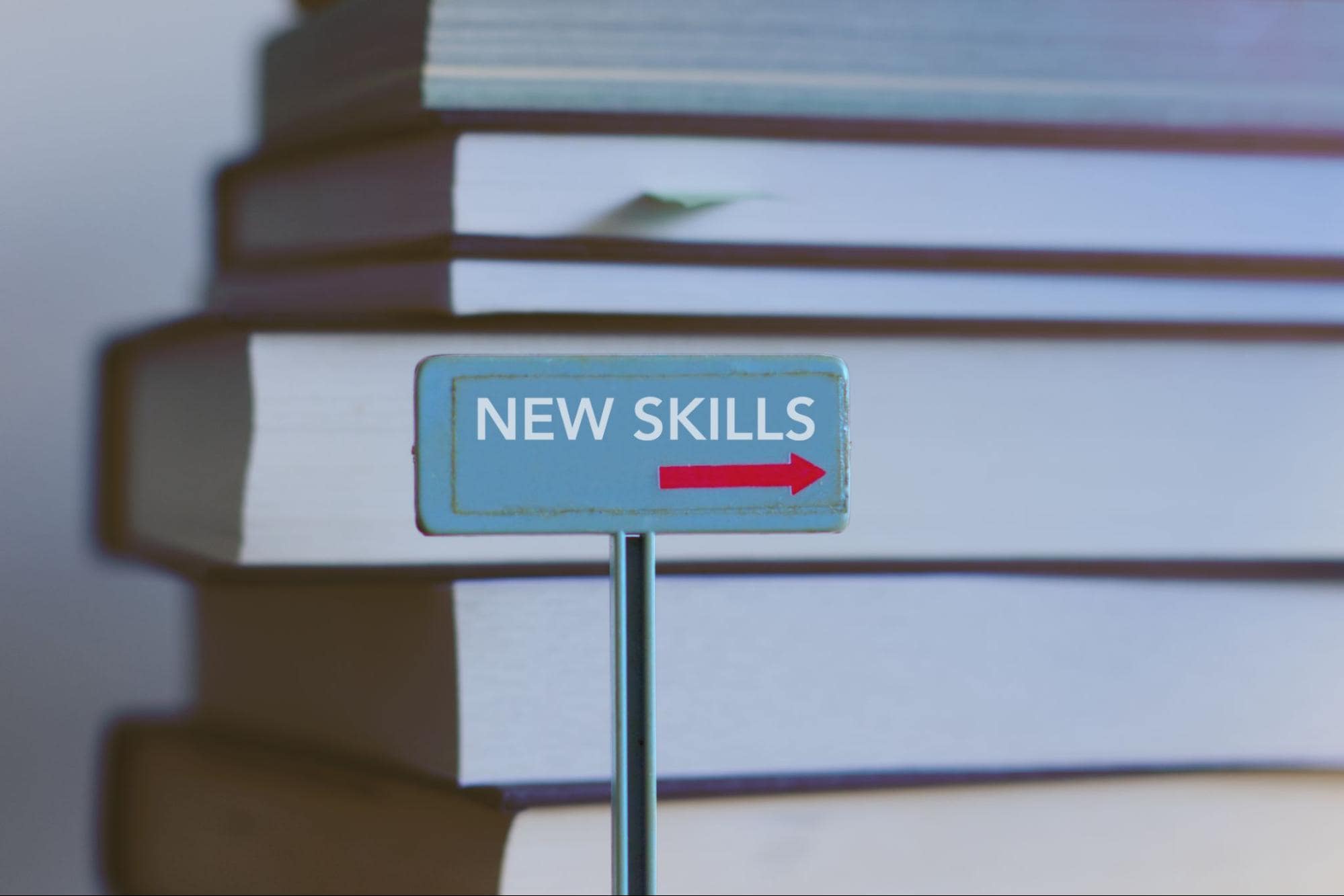
重機の資格ではないものの、現場作業に役立つ資格も多く存在します。そのなかでも取得率の高いものや、現場作業に役立ちそうなものを5つピックアップしました。
自分の職場で必要であれば、取得を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
| 資格 | 資格の詳細 |
| ゴンドラ取扱い業務特別教育 | 高所作業などに使用されるゴンドラの操作をおこなえる |
| アーク溶接等の業務にかかる特別教育 | アーク溶接をおこなえる |
| ガス溶接技能講習 | ガスを用いて溶接や溶断をおこなえる |
| はい作業主任者 | 荷を高さ2m以上に組付ける際や崩せる |
| ロープ高所作業特別教育 | 高さ2m以上の作業現場で、ロープを用いて体を保持させおこなえる |
これらの資格は、建設現場や土木工事で必要になることはもちろん、倉庫業や製造業などでも必要になってきます。すべての現場でそれぞれの資格が必要なわけではありませんが、仕事内容によっては合わせて持っておくことで有利になったり、手当がもらえることもあります。時間とお金に余裕があれば、取得しておくのがおすすめです。
建設機械の整備や管理の資格も存在
建設機械の整備や管理に関する資格は、下記の2つがあります。
2.建設機械レンタル管理士
それぞれの資格を解説します。
1.建設機械整備技能士
建設機械整備技能士を持っていれば、建設機械の点検や整備業務に従事できます。
この資格は国家資格なので、合格率が50%前後と、今回紹介する記事のなかで、一番取得するのが難しい免許です。しかし、持っておけば重機の整備担当になることもできるので優遇される免許でもあります。
特級、1級、2級の3種類があり、特級に関しては深い知識と技術が必要になってきます。受験資格も実務経験もしくは指定学科の卒業と、受験までのハードルも高めです。
2.建設機械レンタル管理士
建設機械レンタル管理士は、日本建設機械レンタル協会が主催、管理する資格です。建設機械への幅広い知識と経験を持っている証として発行されます。
公的資格ではないものの、持っておけば、それだけで知識と経験があると明示できるため、転職などでも役に立つ資格です。
受験資格は実務経験のみで、高卒であれば3年以上、中卒なら5年以上です。受験難易度も低めに設定されています。
重機免許を取得できる代表的な教習所

重機免許を取得できる教習所は全国各地にたくさんあります。そのなかでも規模が大きく、全国的に資格支援をおこなっている団体を紹介します。
コマツ教習所
コマツ教習所は、全国13のセンターを持っている教習所です。
教習所ごとに特色が違い、なかには女性専用コースや外国語コースを開催している教習所もあります。
さまざまな方が気軽に資格取得を目指せる教習所です。
【コベルコ教習所公式ホームページ】
コベルコ教習所
コベルコ教習所は、取得できる資格の種類が多く、講習に合格すれば当日に修了証を発行してくれる特徴を持つ教習所です。
全国各地に教習所を持っており、気軽に資格取得を目指せます。土日のみ開催しているコースもあるので、仕事をしながらでも取得可能です。
【コベルコ教習所公式ホームページ】
厚生労働省でも都道府県別に紹介している
教習所ではないものの、厚生労働省でも都道府県別に教習所を紹介しています。もし、コマツやコベルコの教習所が近くにない場合、こちらのページで教習所を探してみるがおすすめです。
【登録教習機関一覧】
よくある質問
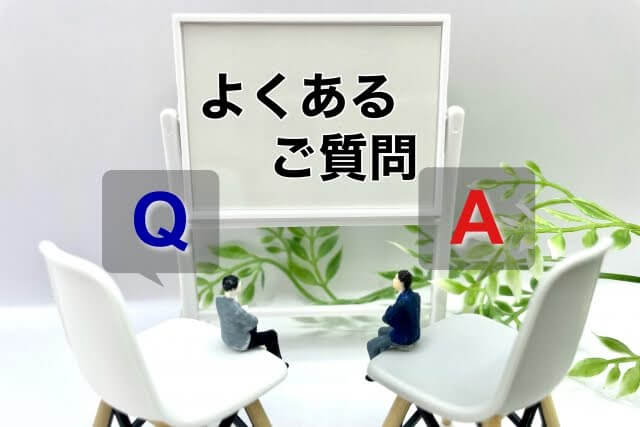
重機免許について、よくある質問をまとめました。
重機免許を女性が取得し働くことができる?
重機免許を持ち、実際に男性に混じって現場で働く女性はたくさんいます。
平成29年におこなった厚生労働省の労働力調査では、昭和60年から平成29年の約30数年で働く女性の人数が約600万人増加したと発表しています。
重機免許に性別の条件はありませんし、重機オペレーターと呼ばれる重機に関するスペシャリストへの道も魅力的です。
重機オペレーターとは資格の種類ではなく、さまざまな重機免許や資格を持つことで、オペレーターの立ち位置で仕事ができることです。
力に自信のない方は、重機オペレーターに進むのも一つの選択肢です。
無免許で重機などの建設機械を運転するとどうなる?
建設機械の運転には、法律で定められた免許が必要です。建設現場で使用される機械は構造が複雑で、安全に操作するための専門知識が求められます。無免許で運転すると重大な事故を引き起こす可能性があり、労働安全衛生法により厳しく規制されています。
無免許で建設機械を運転した場合、作業者には50万円以下の罰金が、また無資格の作業を許可した事業主には6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。さらに、無免許運転による事故は労災認定が受けられないこともあり、作業者の保障にも影響を及ぼします。
建設機械の無免許運転は、作業者の安全だけでなく、現場全体のリスクを高め、企業の信頼にも悪影響を与えます。必ず必要な資格を取得し、免許を携帯したうえで作業に従事しましょう。
まとめ
重機の免許は数え切れないほど多くの種類があります。似たような講習名でも操作できる大きさの制限があったり、特定の重機のみに対応した資格などがあり注意が必要です。
仕事に合った資格を取得し仕事の幅を広げることも大切で、合わせて取得すれば講習時間や料金が安くなる資格もあるので、ぜひ資格取得に励んでみてください。
-
- 重機の免許は数多く存在する
- フォークリフトやクレーンなど使われる頻度の高い免許は人気
- 特殊な現場でしか使わない資格もあるので、仕事に必要な免許の取得が望ましい
- 資格の種類によって操作できる重機の大きさに違いがあるので注意が必要
- ここ数十年で女性の資格取得も増加している






