【2025年最新】トラックの購入に利用可能な補助金・助成金|申請の際の注意点
 トラック購入に関して、資金面での負担を軽減するために活用できる制度がいくつかあります。特に、補助金や助成金は運送業の経営において重要な支援となります。しかし、これらの支援制度は申請手続きが複雑なため、しっかりと理解しておくことが重要です。
トラック購入に関して、資金面での負担を軽減するために活用できる制度がいくつかあります。特に、補助金や助成金は運送業の経営において重要な支援となります。しかし、これらの支援制度は申請手続きが複雑なため、しっかりと理解しておくことが重要です。
本記事では、2025年最新のトラック購入に役立つ補助金・助成金の種類とその利用方法を紹介します。また、トラック購入以外の補助金や助成金も解説しているので、制度を最大限に活用できるようにぜひチェックしてください。
トラック購入に役立つ補助金や助成金とは?

トラックの購入や運送業の経営には、多くの資金が必要です。その負担を軽減するため、国や自治体、関連団体がさまざまな支援制度を提供しています。代表的なものとして 補助金、助成金、融資 があります。それぞれの特徴を理解し、適切な制度を活用することが重要です。
「補助金」 は、国や自治体が政策に沿った取り組みを支援する制度です。申請には審査があり、条件を満たして採択されると支給されます。環境対応トラックの導入支援など、比較的大きな金額が支給されるケースもありますが、募集期間が限られているため注意が必要です。
「助成金」 は、労働環境の改善や人材育成を目的とした支援金で、一定の要件を満たせば受給可能です。例えば、ドライバーの安全教育や健康管理に関する助成金があります。補助金と異なり、申請すれば比較的受け取りやすいですが、給付額は補助金より少額な傾向があります。
「融資」 は、資金を借り入れる制度で、日本政策金融公庫やトラック協会の低金利ローンなどがあります。補助金や助成金と違い返済が必要ですが、自己資金が不足している場合の選択肢として有効です。
これらの制度を上手に活用し、トラック購入や事業運営の負担を軽減しましょう。
具体的に、トラック購入で使える補助金や助成金、融資を以下にまとめました。
| トラックの購入で使える補助金・助成金・融資一覧 | ||
| 全日本トラック協会が実施する助成金 | 安全対策事業 | 安全装置等導入促進助成事業 |
| 環境対策事業 | 環境対応車導入促進助成事業 | |
| アイドリングストップ支援機器導入促進助成事業 | ||
| 国が実施する補助金制度 | 環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業 | |
| 中小トラック事業者向けテールゲートリフター等導入等支援事業 | ||
| その他の助成事業や補助制度 | 低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業 | |
| 商用車の電動化促進事業 | ||
| 公的金融機関 | 日本政策金融公庫 | |
上記に記載した助成金などを中心に、トラックの購入や関連する助成金や補助金、融資についてはこの後に解説していきます。
(参考元:助成制度 | 全日本トラック協会 | Japan Trucking Association)
補助金3種類とそれぞれの利用方法

多くの補助金や助成金の支給は、政府や地方自治体主導でおこなわれるため、補助金制度と聞くだけで「利用は難しいのではないか?」と感じる方が少なくないようです。
確かに補助金や助成金は原資が税金になるので、補助金制度の多くは受給資格が非常に厳しいです。しかし、適切な受給申請をおこない審査に通過すれば補助金や助成金を利用してトラックの導入資金を賄うことは可能です。
トラック購入に対する補助金は、多くが政府や地方自治体主導で支給されることは既に紹介しました。
審査を通過すれば効果的にトラックの導入コストの援助を受けられるので、補助金制度のシステムを掴んでおくことは非常に重要です。
実際にトラック購入に対する補助金は、下記の3つに大別されます。
2.国が実施する補助金制度
3.その他の助成事業や補助制度
それぞれの助成金制度について紹介します。
1.全日本トラック協会が実施する助成金制度
公的援助の色合いが強い補助金・補助金制度ですが、実は運送業務に従事する方にとって馴染みの深い業界団体の「全日本トラック協会」が実施する助成金制度があります。
全日本トラック協会が実施する助成金制度は、以下の3つに分類されています。
・環境対策事業
・経営改善事業
この中からトラックの購入に使える「安全対策事業」「環境対策事業」の助成金を紹介します。
安全対策事業
【安全装置等導入促進助成事業】
安全装置等導入促進助成事業は、会員事業者が新たに購入した安全機器の費用を一部助成する制度です。対象となる機器には、ドライブレコーダーやバックセンサー、サイドビューカメラなどがあり、これらの機器は、事故防止や安全運転支援を目的としています。
助成額は機器の種類により異なり、対象経費の半分(最大上限あり)が助成されます。申請は、指定された期間内におこなう必要があり、事業者の負担軽減に役立つ施策として、多くの事業者に利用されています。
環境対策事業
【環境対応車導入促進助成事業】
環境対応車導入促進助成事業は、会費を滞納していない会員事業者を対象に、令和6年度に新規登録された環境対応車両に助成金を交付します。対象車両は、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車で、車両総重量2.5トン超の新車に限ります。助成金額は車両の種類や重量に応じて異なり、最大150万円まで支給されます。申請には所定の手続きが必要で、地方自治体の助成と併用も可能ですが、事前確認が求められます。
【アイドリングストップ支援機器導入促進助成事業】
アイドリングストップ支援機器導入促進助成事業は、トラックドライバーが休憩や荷待ち時にアイドリングを減らし、燃料消費の削減と環境負荷の低減を目的とした機器の導入を支援します。対象となる機器は、蓄熱マット、蓄冷クーラー、冷蔵車向けスタンバイ装置、エアヒーター、バッテリー式冷房装置で、対象経費の半額(上限あり)が助成されます。さらに、リースや割賦購入も対象となり、導入後は申請書を提出することで助成金を受け取れます。
2.国が実施する補助金制度
国が実施する補助金制度は、以下の2つがあります。
・中小トラック事業者向けテールゲートリフター等導入等支援事業
それぞれの補助金制度を解説します。
環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業
環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業は、二酸化炭素排出削減を目的とした補助金事業です。トラック・バス所有事業者が、ハイブリッドトラックや天然ガス車などの環境配慮型先進トラック・バスを導入する際にかかる経費を補助します。
補助金額は、対象となる環境配慮型先進自動車と同クラスの標準的燃費基準自動車との価格差額の2分の1が補助されます。この取り組みは、トラック・バス運行における二酸化炭素排出削減を目指し、地球環境保全に寄与することを目的としています。事業者は補助金を申請することで、より環境に優しい車両の導入を加速できます。
中小トラック事業者向けテールゲートリフター等導入等支援事業
中小トラック事業者向けテールゲートリフター等導入等支援事業は、効率化や安全性向上を目指す中小トラック事業者向けに、補助金を通じて支援をおこないます。対象事業者は、テールゲートリフター、トラック搭載型クレーン、2段積みデッキなどの導入にかかる費用の最大1/2を補助金として受け取ることができます。また、業務効率化システムや人材採用・育成活動にも支援があり、補助額は1/6の支援も含まれます。これにより、事業者は業務の効率化や安全性向上を図りつつ、経営の強化を目指せます。
3.その他の助成事業や補助制度
全日本トラック協会や国がおこなっている補助制度以外では以下の2つの補助金制度があります。
・商用車の電動化促進事業
それぞれの補助金制度を解説します。
低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業
低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業は、環境省の補助金を活用し、資本金3億円以下または従業員300人以下の中小トラック運送事業者の低炭素型ディーゼルトラック導入を支援する事業です。対象となる車両は、燃費基準を超えた新車ディーゼルトラックで、車両総重量3.5t以上の事業用車両が対象です。
補助額は、車両の排出ガス規制識別記号や廃車の有無により異なり、最大75万円の支援が受けられます。これにより、事業者は燃費改善やCO2削減を進め、低炭素社会の実現に貢献できます。
商用車の電動化促進事業
商用車の電動化促進事業は、温室効果ガス削減とカーボンニュートラルの実現に向け、商用トラックの電動化を支援する事業です。対象となるのは、電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)で、車両総重量2.5トン超の商用トラックや自家用車両です。補助対象者は、貨物自動車運送事業者や自家用商用車を業務で使用する事業者で、環境省の事前登録を受けた車両のみが補助金の対象となります。この事業は、価格低減と業界の競争力向上を促進し、環境負荷の軽減を目指します。
補助金のメリット・注意点
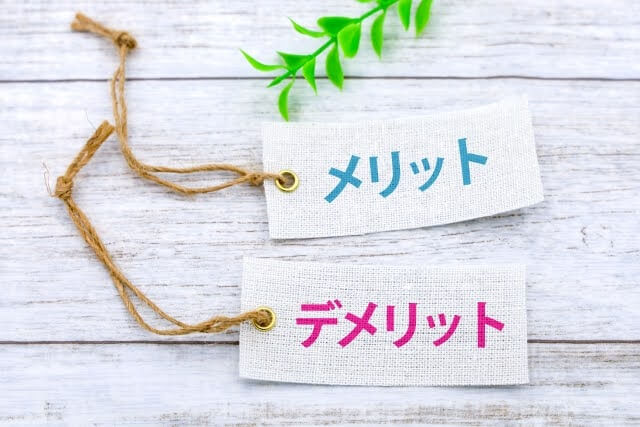
次に、補助金や助成金を使ってトラックを購入するメリットと注意点を紹介します。
補助金や助成金を使ってトラックを購入するメリット
補助金や助成金を活用してトラックを購入する最大のメリットは、車両購入費の負担を軽減できる点です。対象となる車両に限られますが、適用されれば大幅なコスト削減が可能となり、経営の安定にもつながります。
また、補助金や助成金は返済の必要がないため、資金繰りを圧迫することなく事業を拡大できる点も魅力です。加えて、申請過程で事業計画の見直しが求められるため、経営戦略の再評価にも役立ちます。
さらに、受給が認められることで、経営の健全性が証明され、取引先や金融機関からの信用度向上にもつながるでしょう。補助金・助成金制度を上手に活用することで、より安定した経営基盤を築くことができます。
補助金や助成金を使ってトラックを購入する注意点
補助金や助成金を利用してトラックを購入する際には、いくつかの注意点があります。まず、申請から受給までに時間がかかる点です。補助金は事前申請が必要であり、給付までに数か月を要するケースもあります。そのため、すぐに資金が必要な場合は、別の方法を検討する必要があるでしょう。
また、補助金や助成金は必ずしも受給できるとは限りません。募集枠に制限がある場合や、審査基準を満たしていないと判断された場合には、申請しても不採択となる可能性があります。
さらに、補助金は事業の発展を目的とした制度であるため、新たな取り組みや条件をクリアする必要があることが多いです。加えて、補助金は課税対象となるため、受給額に応じた税負担が発生する点にも注意が必要です。
補助金・助成金を活用する際は、最新の情報をチェックし、適用条件や申請期限をしっかり確認したうえで準備を進めることが大切になります。
補助金の対象はトラック購入だけではない

全日本トラック協会の補助金制度にはトラックの購入資金以外の補助金制度が10種類含まれています。10種類の補助金制度の中で運送業を営む方にとって活用しやすいと考えられる補助金を5つ紹介します。
①事故防止対策支援推進事業(国土交通省・TOPPAN株式会社)
事故防止対策支援推進事業は、国土交通省が自動車運送事業者に対して交通事故防止の取り組みを支援するための補助金制度です。この事業では、交通事故リスクを減らすために実施される先進的な対策を支援します。
例えば、先進安全自動車(ASV)を導入するための費用や、運行管理の高度化に向けた設備やシステム導入費用が補助されます。また、過労運転防止のために新たな取り組みをおこなう事業者や、運転手やスタッフに対して安全教育をおこなう事業者にも支援されます。これらの支援を通じて、安全対策を強化し、運送業界での交通事故を減らすことが目的です。
②若年ドライバー確保のための運転免許取得支援助成事業
若年層の雇用確保のため準中型免許と5トン限定準中型免許の限定解除のための指定教習所等の費用を雇用事業者が負担した場合に負担額が給付されます。
この支援は、特例教習の受講や準中型免許の取得に必要な費用を軽減し、事業者が新たに若年ドライバーを雇用する際の負担を軽減することを目的としています。また、普通免許を取得してから準中型免許を新規取得する場合や、5トン限定準中型免許の限定解除にも対応しており、幅広い運転者の育成を支援します。この事業を通じて、トラック業界の若年層の人材確保と育成が進み、将来的な業界の安定性向上が期待されます。
③物流拠点機能強化支援事業(国土交通省)
物流拠点機能強化支援事業は、災害時における物流施設の電力供給を維持し、迅速かつ円滑な物資輸送体制を確保することを目的とした支援制度です。
災害時に停電が発生すると物流に混乱が生じるため、非常用電源(発電設備や蓄電池)の導入が求められています。
この事業では、倉庫事業者、貨物利用運送事業者、トラックターミナル事業者を対象に、非常用電源設備の導入費用の半分(1/2以内)を補助します。
補助対象となる施設は、営業倉庫、航空上屋、トラックターミナルなどです。災害時でも物流が途絶えないようにするため、この事業は企業の負担を軽減し、社会の安定に貢献します。
④エイジフレンドリー補助金(厚生労働省)
エイジフレンドリー補助金は、高齢の労働者を含む従業員が安心して安全に働ける職場環境を整備するための制度です。特に、中小企業が取り組む労働災害防止対策や健康維持・増進のための施策を支援します。
この補助金には主に3つのコースがあります。
60歳以上の労働者の転倒や墜落の防止、腰痛予防、熱中症対策などに必要な設備や対策への補助がおこなわれます。
【転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース】身体機能の低下を防ぐために専門家が提供する運動指導や機能チェックなどにかかる費用が補助対象です。
【コラボヘルスコース】
健康診断結果を活用した禁煙指導やメンタルヘルス対策、健康管理システムの導入など、従業員の健康保持・増進の取り組みに補助が提供されます。
トラック業界では、高齢のドライバーが多く、安全対策や健康維持が重要な課題です。この補助金を活用することで、事故防止や労働環境の改善が期待できます。
⑤団体経由産業保健活動推進助成金(独立行政法人労働者健康安全機構)
団体経由産業保健活動推進助成金は、中小企業や個人事業主が産業保健サービスを受けやすくするための制度です。商工会や事業協同組合などの事業主団体や、労災保険の特別加入団体を通じて助成がおこなわれます。
助成対象には、健康診断結果の意見聴取やストレスチェック後の職場環境改善支援などが含まれ、費用の90%(上限500万円、都道府県事業主団体は1,000万円)が補助されます。
令和4年度に仕組みが見直され、従来の個別事業場対象から団体対象へと変更されました。これにより、多くの事業場が継続的に支援を受けやすくなりました。
トラック業界では、ドライバーの健康管理が安全運転につながります。業界団体を通じた申請で、健康診断の活用やメンタルヘルス対策を進め、従業員の健康を守りながら事業の安定を図りましょう。
補助金以外にもトラックの購入費用に利用できる公的融資

補助金や助成金以外にも、トラックの購入資金に利用できる「日本政策金融公庫」という公的融資があります。信販会社や民間銀行の提供するオートローンなどと比べると審査基準は高くなるものの、低金利で利用できることから新たなトラック導入を検討する場合は資金調達先の1つに加えることをおすすめします。
公的金融機関「日本政策金融公庫」
日本政策金融公庫は株式会社として運営されていますが、政府が100%出資する国営金融機関です。そのため一般的には、公的融資として捉えられています。起業資金や事業資金融資などを中心に低金利での融資をおこなっています。
国民生活事業・中小企業事業・農林水産事業の3つの分野で事業展開しており、トラックの購入資金に活用できる融資制度は中小企業事業の中小企業経営力強化資金が該当します。
この制度を利用して融資を受けると1.16~2.55%の低金利で融資を受けられます。金利については他の金融機関より割安ではあるものの、変動するので利用前に日本政策金融公庫の公式サイトで利率を確認して下さい。
低公害車両関係
日本政策金融公庫の国民生活事業の中に「環境・エネルギー対策資金」という事業があります。この中に低公害車関連として、環境対策の促進を図る事業者に対する融資がおこなわれています。
対象となるのは「天然ガス自動車」、「電気自動車・ハイブリッド自動車」、「プラグインハイブリット自動車」、またはこれらの燃料供給設備とポスト新長期規制等適合車(ディーゼル車限定)を取得する方です。そのため後者のディーゼル車購入であれば該当します。
融資限度額は7,200万円、返済期間は20年以内(据置期間2年以内)で、利率に関しては融資条件によって異なるので詳しくは日本政策金融公庫に確認して下さい。
中古トラックを購入する場合も補助金は利用できる?

国内には多くの補助金や助成金制度が実施されており、トラック購入資金に利用可能なものも多数存在します。これらの補助金や助成金の支給対象は新車購入資金に限定されておらず、中古トラック購入資金も支給対象に該当します。
補助金や助成金の支給を受けられるのであれば、高年式の中古トラックの購入に対する経済的負担が軽くなります。そのため中古トラック販売店での選択肢も、大きく広がるのではないでしょうか。
また公的融資を利用すれば新たなトラックの導入をおこない、事業規模の拡大を目指しやすくなります。公的支援である補助金や助成金、公的融資である日本金融政策公庫の有効活用は機会損失をすることなく確実にビジネスチャンスを掴める方法の1つです。
助成金や補助金を使って中古トラックを購入するなら「トラック流通センター」へ
トラック流通センターでは、補助機や助成金、融資を使ってトラックを購入することが可能です。
トラック流通センターでは用途や希望条件に合わせて、多様な車種やメーカーのトラックを簡単に検索できます。全国の豊富な在庫から選べるため、自分にぴったりの一台が見つかります。
また、市場に出回っていない車両も独自のネットワークを活用してご提案可能です。さらに、納車後も最大1年間の保証が付いているので、購入後も安心して利用できます。
中古トラックをお探しの方は、ぜひ「トラック流通センター」のサイトをチェックしてみてください。
トラック流通センターの中古トラックを見る
まとめ
トラックの購入資金の調達手段として補助金や助成金の活用や公的融資の利用は、非常に効果的だと言えます。公的資金である補助金や助成金、公的融資の活用ポイントは次の3つです。
-
- 全日本トラック協会が実施する5つの助成金制度を活用しよう
- 全ト協公式サイト内で国や外郭団体の補助金制度も確認でき
- 日本政策金融公庫からの公的融資も利用可能






