【最新】自賠責保険証明書とは|データ交付可能に!再発行方法・携帯方法
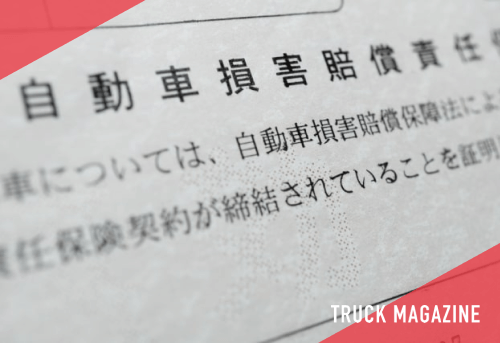 「自賠責保険証明書」は、車両を運転するときは、携帯が義務付けられており、提示できないと罰則が適用されます。紛失した場合は、速やかに再発行しなくてはなりません。また最近では、電子化が進み、スマートフォンで自賠責保険証明書を表示できる「デジタルデータ(電子交付)」も認められています。
「自賠責保険証明書」は、車両を運転するときは、携帯が義務付けられており、提示できないと罰則が適用されます。紛失した場合は、速やかに再発行しなくてはなりません。また最近では、電子化が進み、スマートフォンで自賠責保険証明書を表示できる「デジタルデータ(電子交付)」も認められています。
本記事では、自賠責保険証明書の再発行手続きと電子化された証明書の携帯方法を、具体的な手順や注意点とともに解説します。最後までお読みいただき、万一のときに対応できるよう備えておきましょう。
自賠責保険証明書(自賠責保険証)とは?

自賠責保険証明書(自賠責保険証)とは、自賠責保険への加入を証明する書類です。自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づき自動車を運転する際に加入が義務付けられています。
保険証明書には、証明番号や契約した自動車情報、保険期間などが記載されています。これにより万が一の事故では、被害者への最低限の補償が迅速かつ確実にできる仕組みとなっています。
最近では、紙の証明書に加えてスマートフォンで表示できる電子交付が導入され、加入状況の確認が簡単になりました。
自賠責保険証明書に記載される情報
自賠責保険証明書に記載される主な情報は、次のとおりです。
| 項目 | 記載例 |
| 保険契約者名 | 山田太郎 |
| 契約車両情報 | 普通自動車、車両ナンバーなど |
| 保険期間 | 令和5年4月1日〜令和7年4月1日 |
| 証明書番号 | 1234567890 |
| 保険会社 | ○○損害保険株式会社 |
自動車を運転する際は、こうした内容が記載された保険証明書を常に携帯している必要があるので、再発行や電子データの携帯方法についてもしっかり理解しておきましょう。
ここからは、自賠責保険証明書に記載される情報の中から、3つの重要な項目をピックアップして解説します。
車両情報(自動車登録番号・車体番号・車種)
自賠責保険証明書では、車両が番号で識別されます。具体的には、以下のいずれかが記載されています。
| ・自動車登録番号:運輸支局が管轄ごとに割り振る識別番号 ・車体番号:国土交通省が全車両に対して付与する固有の番号 |
証明書内の種別欄には、車両の使用形態や種類が表記されます。例えば、「自乗」と記載されている場合は、「自家用の乗用車」を示します。これらの情報は、車両を正確に特定するために必要な要素です。記載内容に誤りがないかを必ず確認してください。
契約者情報(氏名・住所)
自賠責保険では、契約手続きをするのは車両の所有者です。そのため、自賠責保険証明書には契約者(所有者)の氏名や住所が記載されます。
なお、結婚や引っ越しなどで氏名や住所が変わった際、証明書の記載内容を変更しなくても、罰則はありません。ただ、古い情報のままだと保険の更新通知が届かない可能性があります。トラブルを防ぐためにも、早めに住所変更の手続きをおこなってください。
保険情報(保険会社名・加入期間・押印)
自賠責保険は国の制度ですが、実際の契約手続きや運営は民間の保険会社が担当しています。そのため、自賠責保険証明書には、加入した保険会社の名称や、保険料の受領を証明する押印や領収書の記載があります。
また、この証明書では、自賠責保険の加入期間を確認することができます。特に 車検を受けるためには自賠責保険の加入が必須であり、加入期間は車検の有効期限をカバーする形で設定されているのが特徴です。
自賠責保険証の自動車登録番号
自賠責保険証明書には、車両番号(ナンバープレート番号)が記載されています。この番号によって、自賠責保険に加入している車両を正確に特定して、保険対象となる自動車を明確化しています。
具体的には、次のような番号が記載されています。
| 記載項目 | 記載例 | 説明 |
| 車両番号 | 品川 500 あ 1234 | 車両のナンバープレートの番号 |
この番号が自身の車両と一致しないと、事故の際に自賠責保険が適用されません。自賠責保険証明書を受け取ったら、自分の車両番号が正しく記載されているかを必ず確認してください。
自賠責保険証明書を紛失して再発行するときも、この番号を伝えられるようにしておくとスムーズです。
自賠責保険証の車台番号
自賠責保険証に記載がある車台番号とは、自動車の個体ごとに割り振られた固有の番号で、戸籍のような役割を果たします。
この番号は、自賠責保険証明書に記載された自動車が、実際に保険加入した車両本人であることを特定するために必要不可欠です。
車台番号は、一般的には自動車のエンジンルーム内や運転席ドア付近、車検証などにも記載があります。
以下に、車台番号の記載例をまとめました。
| 項目 | 記載例 | 記載場所 |
| 車台番号 | ABC-1234567 | 自賠責保険証明書、車検証に記載 |
自賠責証明書のデータ交付方法と注意点

令和6年11月の法改正により、自賠責証明書のデータ交付が可能となりました。
これを受け保険会社では、デジタル版の証明書提供を開始しています。本章では、PDFデータによる自賠責証明書の交付方法と提示方法、交付時の注意点をまとめました。
自賠責証明書のデータ交付方法
データの証明書を発行するには、2つの方法があります。
| ・QRコードを利用する方法:誰でも取得できる ・メール経由で取得する方法:データ交付を希望した契約者のみ利用できる |
それぞれを解説します。
①証明書に記載のQRコードをスマートフォンなどで読み取ります。
②リンク先のダウンロードサイトにアクセスし、QRコード横のパスコードを入力します。
③PDF証明書をダウンロードします。
①契約者のメールアドレスにダウンロード用URLとパスコードが送付されます。
②送付されたURLにアクセスし、メールに記載されたパスコードを入力して、ワンタイムパスワードの送信を選択します。
③契約者のメールアドレスにワンタイムパスワードが送付されるので、そのパスワードを入力し、PDF証明書をダウンロードします。
自賠責証明書(データ交付)の携行・提示について
自賠責証明書をデータ交付(PDF証明書)で管理する場合、スマートフォンなどの端末に保存し、運転時は必ず携行しなくてはなりません。これにより、紙の証明書を携行するのと同じ扱いとなります。
PDF証明書の提示方法は、スマートフォンなどの画面に表示させ見せれば大丈夫です。ただし、整備工場によっては紙の提出を求めることもあるため、紙の証明書も事前に用意しておくと安心です。
なお、運輸支局の窓口では、紙の証明書のみが正式な提示手段とされています。自賠責データが登録情報処理機関に報告されている場合のみ、窓口での提示を省略できます。
自賠責証明書(データ交付)を使用する際の注意点
データ証明書の利用には、以下の点に注意が必要です。
| 注意点 | 詳細 |
| バッテリー切れに注意 | ・端末の充電が切れると証明書を提示できなくなる。 ・事前に充電を確保するか、複数の端末にデータを保存する。 |
| 最新データを所有 | ・契約期間が過ぎた証明書や古い証明書は使用できない。 ・最新のデータを保存しておく。 ・不要になった証明書のデータは、契約者が適宜削除・廃棄する。 |
| 運転者が証明書を持っていない場合の違反リスク | ・契約者がPDF証明書を持っていても、家族や他の運転者がダウンロードを忘れた場合は備付義務違反となる。 |
| 同乗者がデータを持っている場合 | ・車内の誰かがPDF証明書を持っていれば問題ない。 |
| 事故後の対応 | ・事故車両を移動させる際に備付義務が発生する。 ・証明書を保存している人は現場を離れられない。運転者がPDF証明書を所有する。 |
「One-JIBAI」を利用している保険会社【補足】
証明書のデータは、業界共通のシステム「One-JIBAI」を通じて交付します。
2025年3月時点で、以下の保険会社が業界共通システム「One-JIBAI」を使用しています。
本件に関するお問い合わせは、ご契約の代理店または保険会社へ直接ご連絡ください。
| ・あいおいニッセイ同和損保 ・AIG損保 ・共栄火災 ・セコム損保 ・損保ジャパン ・大同火災 ・東京海上日動 ・日新火災 ・三井住友海上 ・楽天損保 ・全国共済農業協同組合連合会 |
(参照・参考元:e-GOV法令検索「自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(令和五年国土交通省令第七号))
自賠責保険証の携帯義務と罰則

自賠責保険証の携帯義務と携帯しなかった場合の罰則について解説します。
自賠責保険証の携帯義務について
自動車やバイク、原付を運転する際は、必ず自賠責保険証明書を携帯しなければなりません。なぜなら、自動車損害賠償保障法により、自賠責保険への加入が義務付けられており、加入状況をいつでも証明できるようにする必要があるからです。
自賠責保険は、万が一の交通事故の際に被害者の救済を目的とした強制保険です。そのため、運転する車やバイクが適切に保険へ加入しているかどうかを、運転者がすぐに証明できるようにしなくてはなりません。
自賠責保険証明書には、保険に加入していることや、有効期限、保険加入期間などの重要な情報が記載されています。万が一、交通事故などのトラブルが発生した際は、この情報を速やかに提示します。原付やバイクではシート下、自動車では車検証と一緒の保管が安心です。
自賠責保険証の不携帯は罰則あり
前述のとおり、自動車やバイクを運転する際は、自賠責保険証明書の携帯が法律で義務付けられています。万が一、携帯せずに運転すると以下の罰則が科される可能性があります。
| 違反内容 | 罰則内容 |
| 賠責保険証明書の不携帯 | ・30万円以下の罰金 ・違反による減点はなし |
| 自賠責保険の未加入もしくは期限切れ | ・1年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・違反点数6点 |
特に自賠責保険に未加入の場合は、即時免許停止となる処分です。必ず有効期限を確認し、期限が切れる前に更新手続きをしてください。
また、紛失した場合は速やかな再発行手続きが求められます。再発行される前に運転してしまうと、不携帯に該当するため罰金刑となります。
自賠責保険証の再発行手続き

自賠責保険証明書は、公道を走行する全ての車両に法律で携帯が義務付けられています。紛失や盗難などで自賠責保険証明書が手元にない場合、再発行手続きをおこないましょう。
本章では、自賠責保険証の再発行手続きについて、方法や必要書類、必要な期間・費用を中心に解説します。
保険証明書を再発行方法
自賠責保険証明書(自賠責保険証)を紛失したら、加入している保険会社で再発行の手続きをします。手続きの際は、加入している保険会社へ連絡するか、最寄りの営業所を訪問してください。
なお、更新の場合は、通常車検の際に販売店やディーラーがサポートしてくれるので、特別な手続きは不要です。ただし、原付(50cc以下)や軽二輪バイク(126cc~250cc)は、ご自身で更新手続きする必要があります。
手続きできる場所は、以下のとおりです。
| ・取扱い保険会社の支店 ・郵便局(一部を除く) ・大手コンビニエンスストア ・インターネット |
加入している保険会社がわからないときは、ディーラーや自動車販売店などの店舗に問い合わせてください。加入している保険会社をすぐに確認できます。
ネットオークションなどの個人売買で車を購入し、自賠責保険の名義変更をしていない場合は、以下の方法で調べましょう。
|
・自賠責保険証明書の印鑑を見て判断し、保険会社に直接問い合わせて、ナンバープレートの登録番号や車台番号を伝えてみる |
再発行するときに必要な書類
自賠責保険証明書を再発行するとき、その理由によって必要な書類が異なります。以下に、必要な書類をケース別にまとめました。
紛失・盗難の場合
以下の書類を持参してください。
| ・印鑑(シャチハタ不可) ・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、印鑑証明書(原本)、パスポート、公的な証明書 など) ・再発行申請書(保険会社の窓口で入手可能) |
損傷して識別が難しい場合
以下の書類を持参してください。
| ・印鑑(シャチハタ不可) ・損傷した自賠責保険証明書(原本) ・車検証(車両情報の確認が必要な場合) |
契約者以外が手続きする場合
以下の書類を持参してください。
| ・再発行申請書への契約者の署名 ・捺印 ・契約者の本人確認書類 |
手続き前に保険会社へ確認しておくとスムーズです。
自賠責保険の更新に必要な書類
必要な書類を表にまとめました。参考にしてください。
| 車種 | 車の例 | 必要書類 |
| 車検が必要な車種 | ・普通自動車 ・小型自動車 ・軽自動車 ・小型二輪(250cc超) |
・自動車検査証(車検証) ・現在契約している自賠責保険証明書 |
| 車検がない車種 | ・原付 ・軽二輪 |
・標識交付証明書(原付) ・軽自動車届出済証(軽二輪) ・現在契約している自賠責保険証明書 |
再発行・更新の際は、必要書類を事前に確認し、スムーズに手続きを進めましょう。契約者以外が手続きする場合は、保険会社へ確認が必要です。
再発行にかかる費用
自賠責保険証明書(自賠責保険証)の再発行は、多くの保険会社で無料ですが、念のため確認しておくと安心です。
なお、自賠責保険を更新する際は、契約期間や用途(自家用・事業用など)、居住地域などによって保険料が異なります。事前に保険会社などに詳細を確認し、必要な金額を準備しておきましょう。
車検のある車両は、車検時に自賠責保険料を支払います。これに対して、原付・250cc以下のバイクなどは、車検がありません。大手コンビニエンスストアや保険会社の窓口で手続きし、保険料を支払います。
再発行までの期間
自賠責保険証明書の再発行は、加入している保険会社で手続きします。保険会社によって多少の誤差はありますが、完了までにかかる期間は、以下のとおりです。
| 手続き方法 | 発行までの目安 |
| 保険会社の窓口で申請 | 即日~1営業日 |
| 郵送で申請 | 1〜2週間前後 |
| 代理店経由で申請 | 2営業日〜2週間前後 |
保険会社の窓口で手続きすれば即日発行も可能ですが、郵送や代理店経由の場合は、1〜2週間程度かかることもあるため、早めの申請をおすすめします。
自賠責保険証明書の不携帯は罰則の対象となるため、手元にない場合は速やかに再発行を申請し、安全に運転できる状態を維持することが大切です。
強制保険である自賠責保険

車やバイクを所有する場合、必ず加入しなければならないのが自賠責保険(強制保険)です。加入を証明するための書類が自賠責保険証明書となります。
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法第5条によりすべての車両(バイク・原付含む)に加入が義務付けられている保険です。未加入のまま運転すると法律違反となり、罰則の対象となります。
この保険は、交通事故の被害者救済を目的としており、対人事故に限定して補償がおこなわれます。補償内容は以下のとおりです。
以下に、損害の種類別に自賠責保険の補償額をまとめました。
| 損害の種類 | 最大補償額 |
| 傷害による損害 | 最大120万円 |
| 死亡による損害 | 最大3,000万円 |
| 後遺障害による損害 | 最大4,000万円(※) |
※後遺障害による損害は、後遺障害の程度によって補償額が異なります。
| ・常時介護が必要な後遺障害(第1級):最大4,000万円 ・随時介護が必要な後遺障害(第2級):最大3,000万円 ・その他の後遺障害(第14級まで):最大75万円 |
(参照・参考元:国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」)
強制保険(自賠責保険)と任意保険の違い
自動車やバイクを運転する際は、強制保険である自賠責保険と、任意保険の両方を理解しておくことが重要です。それぞれの特徴を知り、適切な補償を確保しましょう。
自賠責保険と任意保険の違いを表にまとめました。
| 項目 | 自賠責保険(強制保険) | 任意保険 |
| 加入の義務 | 加入必須 | 任意 |
| 補償の対象 | 対人事故のみで被害者の救済 | 対人・対物・自損事故など幅広い補償 |
| 補償の範囲 | 死亡・傷害・後遺障害に対する賠償 | 対物賠償、車両補償、搭乗者傷害など |
| 補償の上限額 | 死亡事故の場合は最高4,000万円 | 契約内容により無制限も可能 |
| 保険料の設定 | 国が定めた一律料金 | 保険会社ごとに異なる |
任意保険は、自賠責保険ではカバーしきれない部分を補償するための保険です。特に、対物事故や自損事故を補償するためには、任意保険への加入が必須といえます。
主な補償内容は、以下のとおりです。
| ・対人賠償:自賠責保険で不足する賠償分をカバー(無制限も可能) ・対物賠償:他人の車や建物などを壊した場合に補償 ・車両保険:自身の車の修理費用を補償 ・人身傷害補償:運転者や同乗者のケガを補償 |
以下に、任意保険に加入する主なメリットをまとめました。
| ・賠償額の上限が高い(対人・対物で無制限の設定も可能) ・自分の車の修理費用も補償される ・ロードサービスが付帯されることが多い |
自賠責保険は法律で義務付けられていますが、補償範囲が限られます。万が一の事故に備えて任意保険への加入も推奨します。
自賠責保険証明書に関するよくある質問

自賠責保険証明書に関する疑問をQ&A形式でまとめました。
自賠責保険証明書(自賠責保険証)のコピーでも可能?
自賠責保険証明書のコピーは、原則として認められません。道路運送車両法に基づき、車を運転する際には保険証明書の原本を携帯する必要があります。コピーを携帯していても、警察の検問などで指摘を受けた場合、不携帯と見なされる可能性があります。
また、車検時にも原本の提出が求められるため、紛失した場合は速やかに再発行手続きをしてください。
自賠責保険証明書は、加入してからいつもらえる?
一般的には保険に加入した時点で受け取れます。再発行の場合には、最短で約2営業日かかるケースが多いです。
自賠責保険証がない場合どうすればいい?
自賠責保険証明書(自賠責保険証)は、車を運転する際に必ず携帯する重要書類です。しかし、紛失や盗難などで手元にない場合、以下の確認をおこないましょう。
| ・車内や自宅を探す(車検証と一緒に保管していることが多い) ・保険会社に問い合わせる(加入先の保険会社で再発行可能) ・保険期間が切れていないか確認する(期限切れの場合は再契約が必要) |
紛失すると運転できなくなる可能性があるため、日頃から車検証と一緒にしっかり保管し、万が一の際に備えましょう。
どこの自賠責保険に入っているかわからない場合どうすればいい?
自賠責保険を契約している保険会社が分からなくなることもあります。その場合、以下の方法で契約先を特定できます。
| 確認方法 | 詳細 |
| ①車内や自宅を探す | 自賠責保険証明書は通常、車検証と一緒に保管されていることが多い |
| ②車検を受けた整備工場やディーラーに問い合わせる | 車検時に自賠責保険に加入している場合、契約先を把握している可能性がある |
| ③自動車保険(任意保険)の保険会社に問い合わせる | 自賠責保険とセットで契約しているケースも多い |
上記の方法で分からない場合は、自賠責保険調査事務所を利用できます。自賠責保険の契約情報を管理しており、車の登録番号や車台番号を元に契約先を調査してもらえます。
契約先が分からなくても、適切な方法で調査すれば確認できます。万が一に備え、今後は契約情報をしっかり管理し、保険証明書を適切に保管することが大切です。
自賠責保険証を紛失した状態で運転してもいい?
道路運送車両法では、運転時に自賠責保険証明書を携帯しなければならないと定められています。自賠責保険証明書の不携帯の場合は30万円以下の罰金、自賠責保険の未加入(期限切れ)の場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に加えて免許停止処分が課されるため注意してください。
紛失した場合は、すぐに保険を契約した保険会社に再発行を申請しましょう。
自賠責保険のみ加入して任意保険に加入しない場合のリスクは?
自賠責保険に加入していれば安心と思われがちですが、実際には補償範囲が限られており、すべてのリスクをカバーすることはできません。交通事故における主なリスクは以下の4つです。
| ・他人にケガを負わせたり、死亡させたりするリスク(対人補償) ・他人の財産を損壊させるリスク(対物補償) ・自分がケガを負ったり、死亡したりするリスク ・自分の財産を損壊するリスク |
このうち、自賠責保険が適用されるのは対人補償のみです。また、補償限度額も設定されており、傷害による損害は最大120万円、後遺障害は75~4000万円、死亡による損害は最大3000万円までとされています。しかし、実際の交通事故では賠償金が数億円にのぼることもあり、自賠責保険だけでは十分とはいえません。
例えば、他人の建物を損傷した場合や、自分自身が大けがを負い高額な治療費が必要になった場合、自賠責保険では対応できず、すべて自己負担となります。
これに備えるために、任意保険への加入は必要です。任意保険は法的な義務はありませんが、自賠責保険では補償されない対物補償や自己の死亡・傷害補償、車両補償などが含まれています。さらに、対人補償を無制限に設定できるため、万が一の事故にも安心して対応できます。
また、任意保険には盗難や単独事故(電柱への衝突など)、いたずらによる損害をカバーする車両保険もあります。こうしたリスクに備えるためにも、自賠責保険だけでなく任意保険への加入が重要です。
名義変更時は自賠責保険への再加入が必要?
自賠責保険は車両にかかる保険であるため、所有者が変わっても契約期間内であれば再加入の必要はありません。
しかし、名義変更手続きは重要です。法律上の義務ではないものの、手続きを怠るとさまざまなトラブル に発展する可能性があります。
例えば、更新通知が前の所有者に送られることで、新しい所有者が保険の期限を把握できず、気づかないうちに補償が切れるリスクがあります。また、契約者情報が古いままだと、個人情報の漏えいや、万が一事故が発生した際に保険金請求の手続きが複雑になることも考えられます。
新しい所有者が安心して車を運転できるように、名義変更は速やかにおこないましょう。
レンタカーを借りる場合、自賠責保険証明書を確認する必要はありますか?
公道を走るほぼすべての車両は、自賠責保険への加入が義務付けられています。レンタカーも例外ではなく、すべての車両が自賠責保険に加入しています。
レンタカーを貸し出す事業者は、国土交通大臣の許可を受ける必要があり、その審査基準のひとつが「十分な保険補償の確保」です。そのため、レンタカーは自賠責保険に加え、必ず任意保険にも加入しています。
万が一事故が発生した場合、まずは自賠責保険で補償され、不足分があれば任意保険が適用される仕組みです。これにより、利用者は安心してレンタカーを運転できます。
また、レンタカーの利用料金には保険料が含まれているため、追加で自賠責保険や任意保険の手続きをする必要はありません。レンタカーを借りる際は、補償内容を確認し、安心して運転しましょう。
まとめ

自賠責保険証明書は、法律で車両運転時に携帯することが義務付けられています。万が一紛失した場合は、速やかに再発行の手続きをおこなってください。
任意保険は、自分で保険会社を選んで加入するのが一般的ですが、自賠責保険は販売店や車検をおこなう業者が手続きを代行することが多いです。そのため、任意保険とは別の保険会社になる場合があります。自賠責保険証明書を再発行したり、内容を変更したりする際は、加入先の保険会社をご確認ください。
-
- 自賠責保険証明書は、車両が自賠責保険に加入していることを証明する書類で運転時に携帯が義務づけられている
- 令和6年11月から自賠責証明書のデータ交付が開始された。スマートフォンなどにデータを入れておくことで紙の証明書の代わりとして認められる
- 紛失した場合は保険会社にて速やかに再発行の依頼をする。再発行されるまで車両の運転は不可となる






